第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
プログラム
No
タイトル
ダニを抗原とする通年性アレルギー性鼻炎やスギ花粉症では、根本的な治療法である舌下免疫療法が施行されている。スギ花粉症においては舌下免疫療法が始まってから4シーズンが終了し効果や安全性など報告され一般の患者にも認知されるようになってきた。しかし実際の施行例は、花粉症有病者数に比較するとまだまだ少ないようである。外来患者の動向を見ても花粉症や通年性アレルギー性鼻炎患者では、いまだに薬物療法を希望する患者が多く、その薬剤療法の中心になるのが第2世代抗ヒスタミン薬である。
アレルギー性鼻炎は生命予後に関係する疾患ではないことから、 OTC薬の抗ヒスタミン薬を使用する患者も多くみられる。抗ヒスタミン薬は第1世代と第2世代に分類されている。アレルギー性鼻炎治療薬として購入できる OTC薬では、数年前からスイッチ OTCとして数種類の第2世代抗ヒスタミン薬が販売されているが、第1世代抗ヒスタミン薬を含む OTC薬が大多数を占める。ガイドラインではアレルギー性鼻炎治療に第2世代抗ヒスタミン薬を使用することを薦めているが、 OTC薬では患者はどちらの世代の抗ヒスタミン薬も選択することが可能である。
第1世代と第2世代抗ヒスタミン薬においてはヒスタミン拮抗作用を有する基本構造は同じである。第1世代抗ヒスタミン薬は受容体選択性が低く、そのためヒスタミン受容体と相同性ある受容体(ムスカリン受容体など)にも結合し口渇などの副作用が出ていた。ヒスタミン受容体選択性を高くする目的で、第2世代抗ヒスタミン薬は構造上大きな置換基を持つことになり、第1世代のものと比較して分子量が大きくなり、また脂溶性が低下した。このことにより中枢移行が少なくなり眠気などの中枢抑制作用は軽減したが、一方組織移行性については個人差がみられるようになってきた。したがって同一用量では効果が一定しないことがある。
OTC薬を内服していてもアレルギー性鼻炎症状のコントロールが悪いことや副作用があることで処方薬を求めて外来を受診する患者も少なくない。処方するわれわれが第1世代と第2世代抗ヒスタミン薬との差異や特徴について十分理解し、強いまたは弱い抗ヒスタミン薬ということではなく患者ごとに安全性が高く有効な薬剤選択をすることが必要である。
最近アレルギー性鼻炎治療薬として数種類の薬剤が上市されてきた。いずれの薬剤も通年性または季節性アレルギー性鼻炎に対する有効性・安全性が高いことが証明されているが、さらには既存薬剤にはない付加的作用を有する薬剤もある。アレルギー性鼻炎発症メカニズムにおいて、ヒスタミンだけではなく脂質メディエーターの関与も重要である。脂質メディエーターの一つである血小板活性化因子( PAF)に対する拮抗作用を併せ持つ経口抗ヒスタミン薬や、世界で初めてとなる第2世代抗ヒスタミン薬の経皮吸収製剤が開発された。興味あることに、この両者の薬剤は症状増悪時に増量投与(倍量投与)ができることも特徴の一つといえる。皮膚科領域においては蕁麻疹治療において非鎮静性抗ヒスタミン薬の増量投与がすでに推奨されているが、アレルギー性鼻炎においていまだ倍量投与のコンセンサスは得られていない。今後の課題ではないかと思われる。
経皮吸収剤の抗ヒスタミン薬アレサガⓇテープの主薬は1993年に発売され経口抗ヒスタミン薬として使用されてきたエメダスチンである。ドラッグデリバリーシステム( DDS)の技術要素の中で薬剤吸収改善を目的とした輸送担体の工夫や投与ルートの変更を考慮して開発されたものである。経口内服薬から経皮吸収薬に切り替えることにより投与回数が減ったことや肝代謝を受けない、また貼付している間の薬物血中濃度が一定に保たれるなどの利点がある。経口剤としてエメダスチンは高い有効性を示したが眠気の副作用がやや多くみられた。アレサガ Ⓡテープのこれまでの臨床試験では眠気の頻度は極端に高いものではなかった。
この講演では、第1世代および第2世代抗ヒスタミン薬の構造的な差異について概説し、最近上市された薬剤についての効果などについて紹介する。
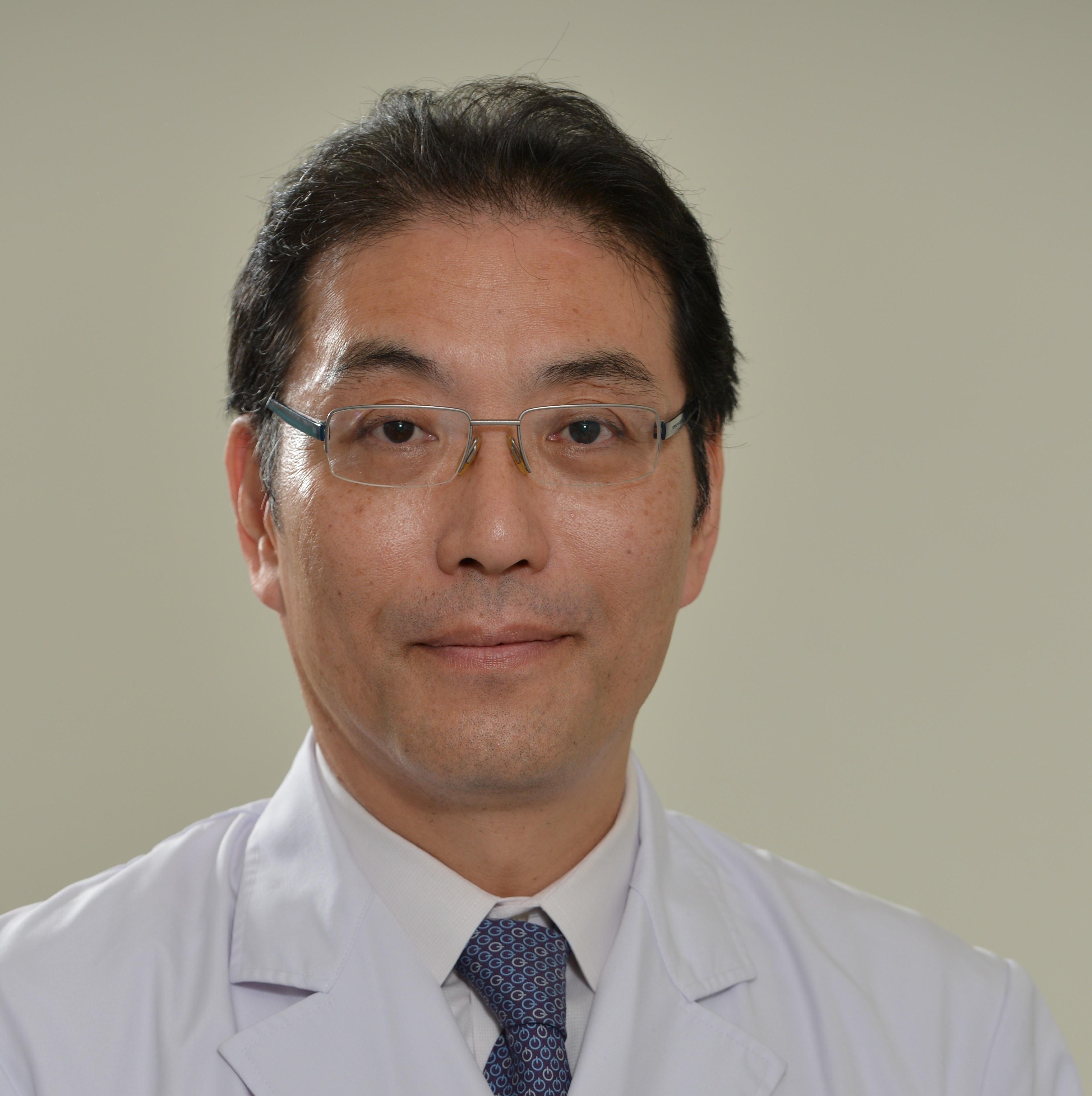
橋口一弘
1982年 慶應義塾大学医学部卒業
1982年 慶応義塾大学病院耳鼻咽喉科入局
1986年 慶應義塾大学病院耳鼻咽喉科助手
1989年 産業医科大学耳鼻咽喉科講師・医学博士
1990年 北里研究所病院耳鼻咽喉科勤務・日本耳鼻咽喉科専門医
2000年 北里研究所病院耳鼻咽喉科部長
2009年 北里大学北里研究所病院臨床教授
2011年 ふたばクリニック院長
2019/05/09 13:00〜13:50 第2会場