第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
プログラム
No
タイトル
手術を円滑に進め、副損傷を避けるための第一は、解剖の把握にあることは言うまでもない。本セミナーの前半では手術操作に必要な副鼻腔の解剖とそのバリエーション、留意点について CT画像を中心に概説する。
【篩骨洞】
篩骨洞は上顎洞、前頭洞、蝶形骨洞を開放する際に操作が必須であり、副鼻腔手術の要となる構造である。残りの3洞がいずれも骨の内に空洞がくりぬかれた文字通りの“洞”であるのに対し、篩骨洞の構造は鼻道という軒下に基板という仕切りの骨壁が並んでいる構造であり、手術ではこれを順番に切除していく。ただし基板といっても決して平らな構造ではなく、凹凸の多いかつ個体差の多い骨板である。
篩骨洞手術ではまず鉤状突起が切除されるが、鉤状突起と眼窩紙様板の距離は症例によって差があり、近接している場合は安易にメスで切除すると紙様板を損傷する可能性がある。また篩骨洞の天蓋の内方に篩板が存在し、これが篩骨洞天蓋に比べて低位であった場合内側の操作により髄液漏の可能性がある。前篩骨動脈の走行が篩骨洞内に突出していることがあり、この場合前篩骨洞内の操作で不用意に天蓋の病変の切除を行うと損傷する可能性がある。
【上顎洞】
上顎洞の自然口は鉤状突起の後上方にあり、直視できないので自然口の開放に際してはまず鉤状突起を切除することになる。自然口の拡大を前方に過度に行うと鼻涙管が損傷され術後導涙障害を来すことになり注意が必要である。また上顎洞の後上方または後上方から眼窩下壁の前方まであたかも上顎洞が上下に2分されているかのような形態をとることがある。これは上顎洞の後上方に篩骨洞(主として後部篩骨洞)が発達して進展したものでハレル蜂巣( Haller’s cell)と呼ばれる。これが存在する場合は開放を行わないと上顎洞が大きく開放されないことが多い。歯科治療の変化に伴って歯性上顎洞炎が増えており、一側性の上顎洞炎をみた場合は必ず歯根との位置関係や根尖病巣の有無を確認する。
【蝶形骨洞】
蝶形骨洞は全副鼻腔の中で最深部に位置し、視神経、内頸動脈などの重要構造物と近接する。蝶形骨洞の大きさは個人差、左右差がかなり大きいため、術前に CTを確認して開窓のルートをイメージしておく。内視鏡下で蝶形骨洞にアプローチする場合、一般的なのは蝶形骨洞自然口または篩骨洞を経由する方法であろう。蝶形骨洞の自然口は通常洞の上下の広がりのほぼ中央にあり、これは上鼻甲介の天蓋付着部と上鼻甲介の後端のほぼ中央の高さである。開口部が正中に近い場合は見つかりやすいが、蝶篩陥凹が外方に深い場合は外側に自然口がある場合があり見つかりにくい。篩骨洞経由のアプローチでは自然口の高さでできるだけ内側の位置の前壁を開放する。
後部篩骨洞の発育が良好な場合に蝶形骨洞の上に覆いかぶさるように存在することがあり、これをオノディ蜂巣( Onodi cell)と呼ぶ。オノディ蜂巣が存在する場合、視神経管隆起は多くが蝶形骨洞内ではなく同蜂巣内に出現する。
またオノディ蜂巣の発育が良好で蝶形骨洞が下方に圧排されている場合、前者を蝶形骨洞と誤認することがあり得る。開放された空間が蝶形骨洞自然口と連続していることをゾンデや鑷子を慎重に使用して確認する。もし術前の CTのプランニングで困難が予想される場合はナビゲーションがあると便利である。蝶形骨洞と Onodi蜂巣の位置関係、およびタイプ別の開窓の仕方については和田らの優れた論文( Int Forum Allergy Rhinol 5 : 1068―1076, 2015)があり、参照していただきたい。
また蝶形骨洞自然口の下方には中隔後鼻動脈が横走しており、損傷するとかなりの出血を見るので留意が必要である。
【前頭洞】
前頭洞も解剖学的に個人差が大きい副鼻腔である。前頭洞の排泄路は後方に頭蓋底、側方に眼窩があるためほかの3洞に比べて開大に限界がある。さらに前頭洞の下方には前方に鼻堤蜂巣および frontal ethmoidal cell、後方に frontal bulla cellなどの前部篩骨蜂巣群が存在し、排泄路を複雑にしている。
前頭洞排泄路の視認のしやすさは鉤状突起の上方の付着の様式によって異なり、一番多いタイプである紙様板に付着するタイプでは鼻堤蜂巣の内後方から後方に開口部があり、交通路が狭いため直ちには前頭洞内部が見えない。一方鉤状突起が頭蓋底に付着し、前頭洞排泄路が鈎状突起の外側に位置する型では鉤状突起の上部を除去すると比較的容易に前頭洞口が確認される。前頭窩の前方には危険物はないが、後方は前頭洞後壁から篩板に連続して頭蓋底が存在しており、後方の壁を不用意に拡大すると髄液漏を来すので注意が必要である。
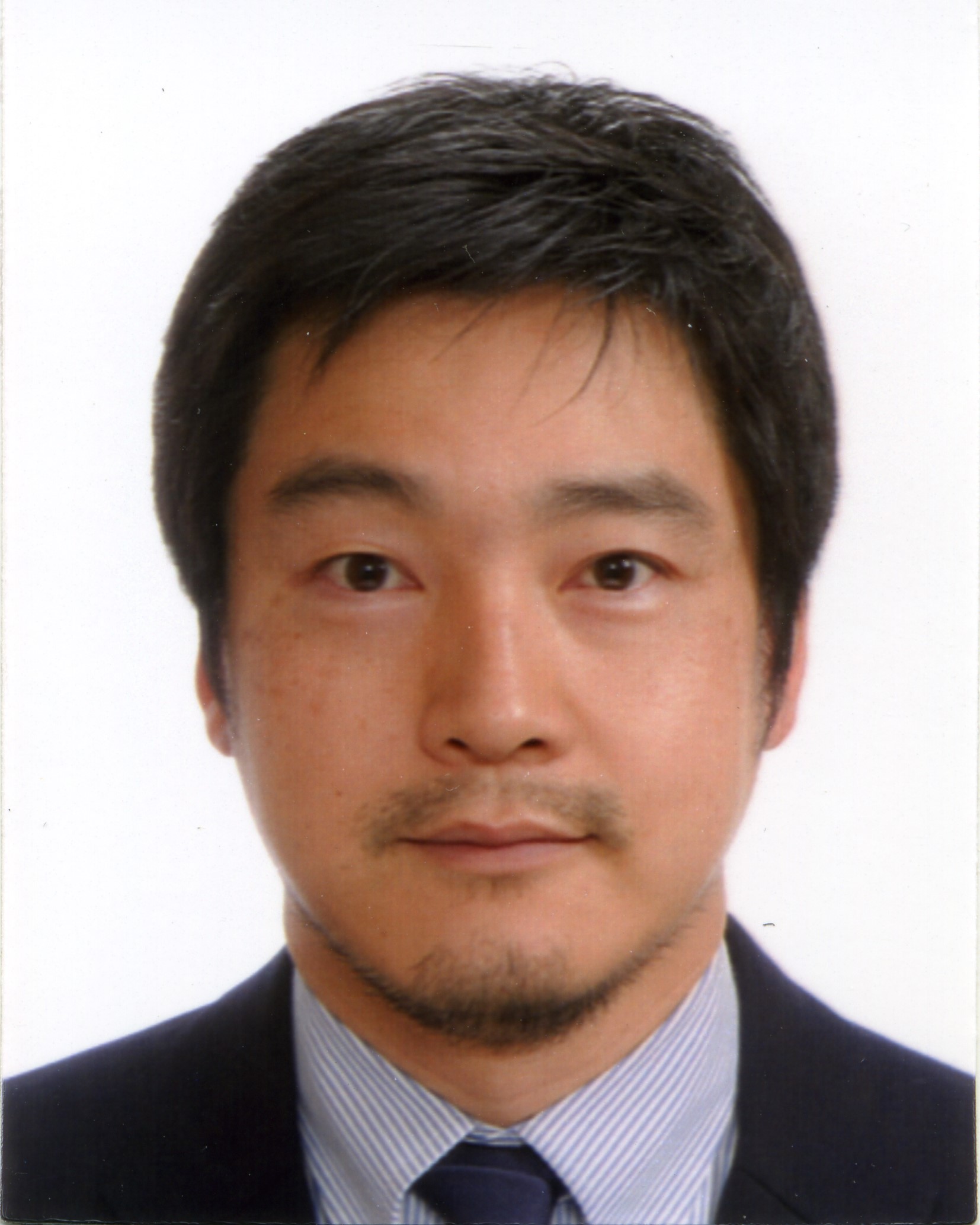
近藤健二
1994年 東京大学医学部卒業
東京大学耳鼻咽喉科入局
2001年 東京大学大学院医学系研究科修了
2004年~05年 カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部耳鼻咽喉科博士研究員
2008年 東京大学耳鼻咽喉科講師
2016年 東京大学耳鼻咽喉科准教授
2019/05/10 8:00〜9:00 第7会場