第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
プログラム
No
タイトル
はじめに
高齢者の定義はさまざまあるが、わが国では65〜74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と規定している。2017年生まれの日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.26年であるが、今年高齢者(65歳)となる昭和29年生まれ(1954年)の当時の平均寿命は男性63.41年、女性67.69年であった。社会や医療の発達により寿命が大きく伸びてきたことから、2005年には世界に先駆け超高齢社会を迎えた。平成28年度(2016年)版「高齢社会白書」では、65歳以上の高齢者人口は3,392万人(総人口の26.7%)に達し、後期高齢者は12.9%となった。これに伴い、疾患死亡における悪性新生物の割合は増加の一途をたどり、高齢者の死亡原因として「がん」が40%を占めている。
こうした中で、高齢という理由だけでがんに対する根治的治療を行わないわけにはいかない。なぜならば現在の日本人平均余命は、75歳時の男性12.18年、女性15.79年であり、85歳時でも男性6.26年、女性8.39年と根治を目指せる年数が示されているからである。平均余命が5年前後になるのは男女とも90歳時であるので、こうしてみると高齢者のほぼ全員に治療を前提としたアセスメントをしなければならない時代がやってきたと考えなければならない。
高齢がん患者に対するリスク評価
高齢者においては、生理学的な変化による臓器・身体機能低下、多病・多剤内服、社会的機能低下など非高齢者とは異なった多様な患者背景が生じている。そのため、がんによる死より平均余命が長いと判断される場合は、治療予定の患者ごとに身体的機能、意思決定能力、治療目的と価値観、栄養状態、持病、家族の介護力などを総合的に評価して標準治療を含む治療法選択を示すことが求められる。
高齢癌患者の評価法として、 NCCNガイドライン Older Adult Oncology( version 1.2019)で示されているものが高齢者総合的機能評価( CGA)である。これは ⑴ ADL(日常生活動作)、⑵ IADL(手段的日常生活動作)、⑶認知機能、⑷気分(抑うつ・意欲)、⑸コミュニケーション、⑹社会的環境(人的環境・介護環境)の6分野を25の質問を用いてスクリーニングし、必要に応じて追加のテストを行い評価するものである。しかし、多岐にわたる検査は長時間を必要とし、日常診療に手軽に取り入れられるものではない。簡易版が求められる所以である。
頭頸部外科医としては、術後合併症の発生を予防するための術前全身状態評価やリスク評価システムを求めている。高齢者胃癌や大腸癌、肺癌症例に対するリスク評価法として estimation of physiologic ability and surgical stress( E- PASS)が有用とされているが、頭頸部癌に対する検討はほとんどされていない。こうしたツールの利用はこれからの課題である。一方、フレイルあるいはサルコペニアなどの概念が注目されてきている。フレイルとは加齢に伴うさまざまな機能変化や予備能力低下によって健康障害に対する脆弱性が増加した状態であり、サルコペニアは筋肉量と筋力の進行性かつ全身性の減少に特徴づけられる症候群である。これらにあてはまる患者では、術後合併症や在院死が有意に多くなるとされている。それ故こうした患者を扱うわれわれは、栄養状態の評価と対策を身に着けることが必要となってきている。このほか、術後管理での問題に術後せん妄が挙げられる。対策として環境を日常の状態に近づける非薬物的介入や早期リハビリによる早期離床を促すことが勧められているが、最近、 ICUにおけるデクスメデトミジン(プレセデックス®)による鎮静が、せん妄の頻度を減らすとのメタ解析が報告された。
治療法選択
別府らは後期高齢頭頸部癌患者208例において147例(70.7%)に根治治療が行われたと報告している。そのうち根治手術症例は86例(41.3%)であり、頸部郭清術が59例(28.4%)、再建手術が26例(12.5%)に行われていた。頸部郭清を簡略化した症例は3例のみであり、再建を要する切除症例は全例再建が行われていた。治療成績も非高齢者症例と遜色ない成果が得られており、高齢者においても非高齢者と変わらぬ治療方針、手術術式を施行することが可能であると述べている。
宮城県立がんセンターでは、85歳以上の超高齢者38例(開院1993年〜2005年)に対して検討がなされた。2年粗生存率は姑息治療13例:12.7%、根治治療18例:65.2%と有意差( p< 0.0005)を認め、超高齢者でも治療可能な症例に対しては予後が期待できることが報告された。また、根治治療例の死因はほとんどが他病死であったことより、可能な限りシンプルな治療法で治療すべきと考えられた。
さいごに
現在、わが国には高齢者のがん治療に対する指針はなく、医師が個々の状況に応じて判断している。 JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)の高齢者研究委員会において高齢者のがん治療の基準を作ろうとする動きが始まっており、その提言に注目したい。
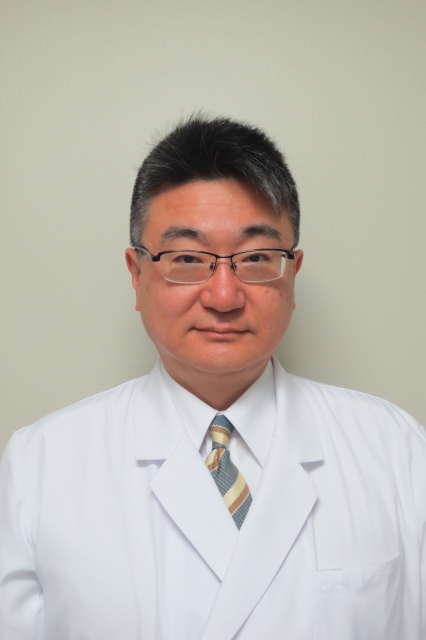
松浦一登
1990年 東北大学医学部卒業ならびに東北大学医学部耳鼻咽喉科入局
2002年 国立がんセンター東病院外来部頭頸科医師・中央病院頭頸科医師(併任)
2004年 宮城県立がんセンター頭頸部外科 診療科長
2014年 東北大学大学院医学系研究科連携講座 頭頸部腫瘍学分野教授(併任)
2014年 金沢医科大学医学部頭頸部外科 客員教授(併任)
2017年 宮城県立がんセンター 医療局長
2018年 宮城県立がんセンター 副院長
2019/05/11 10:25〜11:25 第8会場