第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
プログラム
No
タイトル
【研究の背景】
われわれの2017年最新疫学調査では、スギ花粉症の発症率が成人で40%、通年性を加えると約60%となっており、まさしくアレルギー性鼻炎・花粉症は、国民病となっている。その経済損失は日本全体で年間4兆3,966億円と推計され、大きな社会問題である。多くの患者は抗ヒスタミン薬などで軽快するが、通常の薬物治療が無効で経口ステロイドを必要とする例、高度鼻閉のため手術に至る例も存在する。舌下免疫療法も行われているが約30%は効果がない。申請者はこのような症例を「難治性」と考えているが、いまだ難治性の共通見解はない。これら難治性症例では、春季カタルなど眼症状、皮膚の痒み、咳(喘息)、口腔アレルギーなどの鼻以外のアレルギー症状を合併している可能性が高く、全身的な見地からの検討が必要と考える。
【目的】難治性アレルギー性鼻炎、難治性花粉症を定義し、鼻アレルギー診療ガイドラインに反映させるとともに難治化因子を探索する。
【方法】
①日本鼻科学会員(約2,000名)、日本アレルギー学会専門医(約4,000名)に対して、郵送による難治性アレルギー性鼻炎・花粉症の見解を問うアンケート調査を行う。 ②開業医・勤務医において、花粉症・アレルギー性鼻炎診療における難治性と考える患者を抽出し、通常の抗ヒスタミン薬に効果がある症例の特徴をケースコントロールスタディで比較検討する。大都市(東京・大阪)、都市(千葉・岡山)、地方(秋田・福井)、口腔アレルギーが多い北海道を対象とする。
③アレルギー性鼻炎に対する手術を行った患者のアレルギー合併症、感作状況を含めた背景因子を検討する。
④舌下免疫療法不応答患者の遺伝子を調べ、遺伝環境要因の同定を行う。
【特色・独創性・成果】
①合併症の実態を把握することにより、難治性アレルギー性鼻炎・花粉症の定義を確立し、ガイドラインへ反映させる。
②手術症例の検討により、手術回避への先制医療が確立できる。
③舌下免疫応答性を遺伝子レベルで明確にする。
④難治性は国際的に確立されていないので、日本から発信するとともに、難治化因子の探索をし、次なる新しい治療法・先制医療のシーズとする。
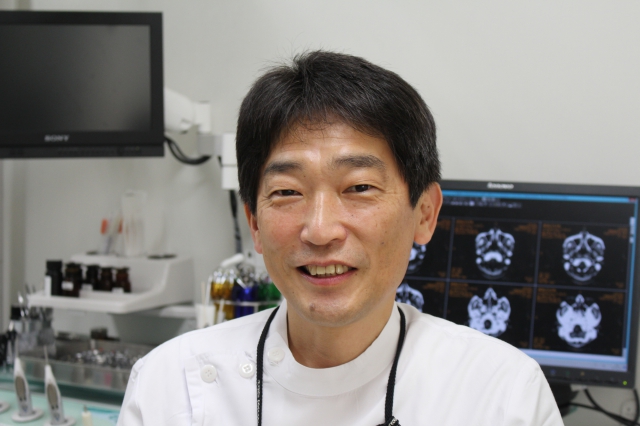
藤枝重治
1986年 福井医科大学医学部医学科卒業
1993年 米国UCLA臨床免疫アレルギー科に文部省長期在外研究員として滞在
1995年 帰国
1996年 福井医科大学医学部附属病院講師
2002年 福井医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座教授
2003年 福井大学・医学部・感覚運動医学講座・耳鼻咽喉科頭頸部外科学教授
2010年 福井大学医学部附属病院副病院長(現在:経営-医療安全)
2019/05/09 16:00〜17:30 第7会場