第120回 日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
プログラム
No
タイトル
超高齢社会を迎え、認知症の増加が社会問題となっている。また、加齢性難聴をはじめとする感覚障害も超高齢化とともに急増している。2015年、厚生労働省は「認知症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜」の戦略として新オレンジプランを発表したが、このプランの中で認知症の危険因子に初めて難聴が加えられた。また、海外でも認知症と難聴との関係が検討され、そのレビューとして、2017年7月に Lancetに発表された「 Dementia prevention, intervention, and care」で医学的介入が可能な危険因子はとして難聴が9%と最も影響が大きいと報告されたのを契機に、耳鼻咽喉科疾患と認知症との関係が社会的にも注目されるようになっている。
認知症とは、アルツハイマー病やレビー小体病、脳血管疾患など、さまざまな原因によって脳に器質的障害が生じ、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下し、日常生活に支障を来す状態と定義されている。症状は大きく、中核症状と多彩な BPSD( behavioral and psychological symptoms of dementia)と呼ばれる行動・心理症状に分けることができる。中核症状とは、認知症では必ず生じる症状で、失認、失行、失語、記憶障害や実行機能障害などがある。一方、 BPSDとは、本人がもともと持っている性格や生活環境、人間関係などのさまざまな要因が関与して生じる症状で、不安や抑うつ、興奮、徘徊、不眠、妄想、不潔行為、食行動異常などがある。認知症は平成24年の統計で約462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と推計されている。認知症の予備群である軽度認知障害を MCI( mild cognitive impairment)と呼ぶが、この軽度認知障害も約400万人と推計されており、高齢者の約4人に1人が認知症またはその予備群ということになる。超高齢化が進む中で、今後も認知症が急速に増加すると見込まれており、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる平成37年には、認知症と軽度認知障害が共に約700万人、つまり合わせると1,400万人に達すると予測されており、認知症対策はわが国の医療にとって喫緊の課題となっている。
認知症は以前、痴呆などと呼ばれてきたが、昭和61年に厚生省は痴呆性老人対策本部を初めて設置した。平成16年には厚生労働省の「痴呆に替わる用語に関する検討会」の報告を受け、痴呆から認知症へと呼び方を変更した。そして、「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」の構想が展開された。平成25年、厚生労働省は認知症対策として、総合的に認知症に取り組む国家戦略としてオレンジプラン、すなわち認知症施策推進5ヵ年計画を発表したが、平成26年11月に開催された「認知症サミット日本後継イベント」における、世界10カ国以上からの300人を超える専門家による「新しいケアと予防のモデル」をテーマとした議論を受けて、平成27年1月27日、「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」に改定した。これが新オレンジプランであり、厚生労働省が内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省などの関係省庁と共同して策定したもので、今日、認知症高齢者等の日常生活全体を支えていくための基盤となっている。新オレンジプランの対象期間は認知症有病者が700万人に達すると推計される平成37年までで、旧オレンジプランの骨子を踏襲しつつ、目標値の引上げなどの具体策が盛り込まれた。
このように認知症対策はわが国の厚生労働行政および医療の現場での喫緊の課題になっており、耳鼻咽喉科診療上も大きな問題となっている。今回の本シンポジウムでは耳鼻咽喉科と認知症の関係についての現状を各領域の第一人者に概説していただく予定である。基調講演として、わが国の認知症研究のリーダーの一人である国立長寿医療研究センターの佐治直樹先生に「認知症医療と研究に関する最近の話題:オレンジレジストリ研究と感覚機能」と題したを講演をいただき、次いで認知症と聴覚障害との関係について内田育恵先生(愛知医大、国立長寿医療研究センター)、前庭障害との関係について堀井新先生(新潟大)、嗅覚障害との関係について三輪高喜先生(金沢医大)、そして睡眠との関係について宮崎総一郎先生(中部大学)に各々ご講演をいただくことにしている。耳鼻咽喉科疾患と認知症の関係についての初めてのシンポジウムであり、認知症を取り巻く諸問題に対する耳鼻咽喉科としての今後の取り組みの方向性や課題を整理する機会としたい。
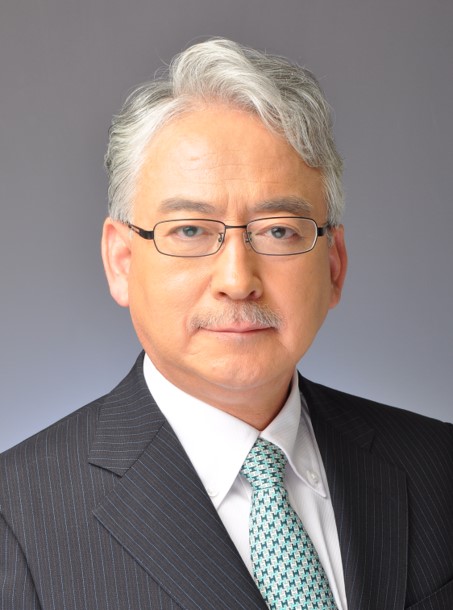
小川郁
1981年 慶應義塾大学医学部卒業
1983年 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科助手
1991年 ミシガン大学 クレスギ聴覚研究所研究員
1995年 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科専任講師
2002年 慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科教授
2015年 慶應義塾大学医学部長補佐
2017年 慶應医師会会長
2019/05/10 15:20〜17:20 第1会場